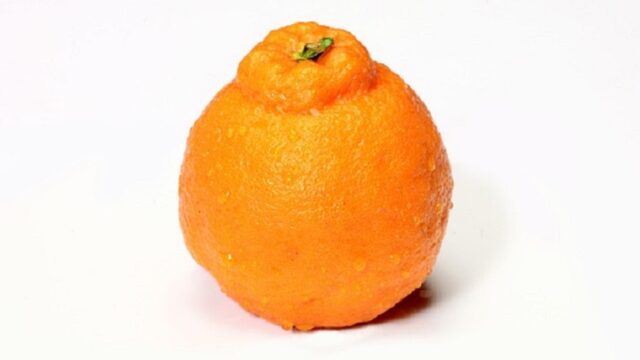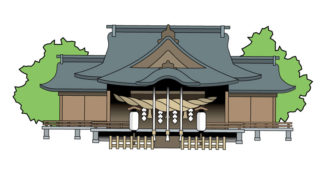2026年の二十四節気一覧と月日や意味を合わせてご紹介します!
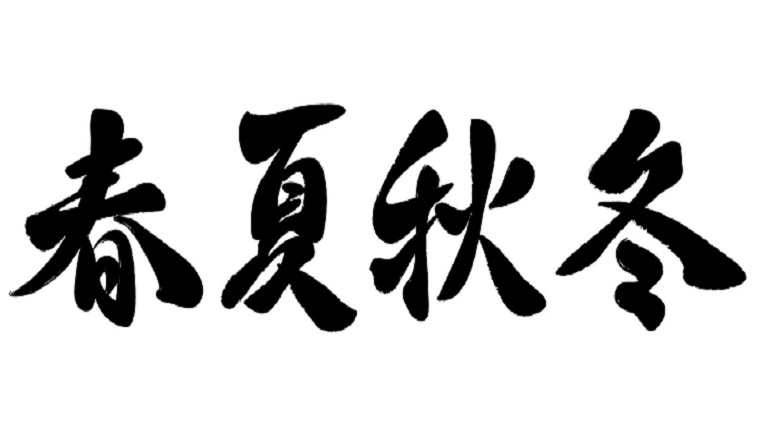
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
目次
二十四節気とは
この記事では、2026年(令和8年)の二十四節気(にじゅうしせっき)を一覧でご紹介します。また、2026年の二十四節気それぞれの月日と、二十四節気それぞれの意味も合わせてお伝えします。
ところで二十四節気とは何でしょうか。
二十四節気は紀元前の中国で考案されたもので、1年を24等分してそれぞれに季節を表す言葉をつけたものです。
当時の暦と、現在の暦は異なるので、必ずしも今の季節感を端的に示すものではありませんが、それでも二十四節気は今でもしっかりと残っています。
現在の1年は、1月に始まり、12月で終わります。
それに対して二十四節気は、現在の暦では2月の立春に始まり、1月の大寒で終わります。
このように現在の暦と二十四節気では、始まりも終わりも異なりますが、ここでは現在の暦に合わせて、2026年の二十四節気それぞれの月日と意味をお伝えします。
まずは、二十四節気全体を一覧でご紹介します。
二十四節気一覧
二十四節気は1年を24等分して、それぞれの季節を表す言葉をつけたものです。日本には春夏秋冬がありますが、春夏秋冬には二十四節気のうち6つずつがあてはめられています。
まずは、それぞれの季節に入る二十四節気を一覧でお伝えします。
なお、春夏秋冬のそれぞれの始まりは、立春・立夏・立秋・立冬で、「立」という字には「始まり」という意味があります。
二十四節気一覧
| 春を表す二十四節気 | 立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨 |
| 夏を表す二十四節気 | 立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑 |
| 秋を表す二十四節気 | 立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降 |
| 冬を表す二十四節気 | 立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒 |
スポンサーリンク
2026年(令和8年)1月から6月までの二十四節気
2026年1月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 小寒 | しょうかん | 1月5日 | 冬 |
| 大寒 | だいかん | 1月20日 | 冬 |
また、小寒から春の始まりである、立春の前日(節分)までを「寒の内」と称しています。
小寒の次の大寒は、1年のうちで最も寒い時期を意味しています。寒の内の中間にある二十四節気です。
■合わせて読みたい
2026年2月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 立春 | りっしゅん | 2月4日 | 春 |
| 雨水 | うすい | 2月19日 | 春 |
雨水は、それまでの雪が雨に変わる頃という意味があります。また、雨水の頃からその年の農作業の準備を始めることも多かったようです。
■合わせて読みたい
2026年3月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 啓蟄 | けいちつ | 3月5日 | 春 |
| 春分 | しゅんぶん | 3月20日 | 春 |
春分は、春の季節の中間を意味しています。概ねですが、昼の時間と夜の時間が同じになります。
また、春分の日前の3日間、後の3日間の合わせて7日間が、春の彼岸になります。
■合わせて読みたい
2026年4月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 清明 | せいめい | 4月5日 | 春 |
| 穀雨 | こくう | 4月20日 | 春 |
穀雨は、雨が多くなり穀物の種をまく時期であることを意味しています。
■合わせて読みたい
2026年5月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 立夏 | りっか | 5月5日 | 夏 |
| 小満 | しょうまん | 5月21日 | 夏 |
小満は暖かさが続き、万物が一定の大きさに成長することを意味しています。
■合わせて読みたい
2026年6月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 芒種 | ぼうしゅ | 6月6日 | 夏 |
| 夏至 | げし | 6月21日 | 夏 |
夏至は1年の中で昼が最も長く、夜が最も短い日になります。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
2026年(令和8年)7月から12月までの二十四節気
2026年7月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 小暑 | しょうしょ | 7月7日 | 夏 |
| 大暑 | たいしょ | 7月23日 | 夏 |
大暑は、1年の中でも最も暑い時期であるという意味があります。
■合わせて読みたい
2026年8月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 立秋 | りっしゅう | 8月7日 | 秋 |
| 処暑 | しょしょ | 8月23日 | 秋 |
処暑には、厳しい暑さが収まってくるという意味があります。
2026年9月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 白露 | はくろ | 9月7日 | 秋 |
| 秋分 | しゅうぶん | 9月23日 | 秋 |
秋分は秋の季節の中間を意味しています。概ねですが、昼の時間と夜の時間が同じになります。
また、秋分の日前の3日間、後の3日間の合わせて7日間が、秋の彼岸になります。
■合わせて読みたい
2026年10月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 寒露 | かんろ | 10月8日 | 秋 |
| 霜降 | そうこう | 10月23日 | 秋 |
霜降は、朝に霜が降りる時期がきたことを意味しています。
2026年11月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 立冬 | りっとう | 11月7日 | 冬 |
| 小雪 | しょうせつ | 11月22日 | 冬 |
小雪は、雪は降るが量は少ない時期を意味しています。
■合わせて読みたい
2026年12月の二十四節気
| 名称 | 読み方 | 月日 | 季節 |
| 大雪 | たいせつ | 12月7日 | 冬 |
| 冬至 | とうじ | 12月22日 | 冬 |
冬至は1年の中で昼が最も短く、夜が最も長い日になります。
■合わせて読みたい
まとめ

この記事では2026年(令和8年)の二十四節気一覧とともに、二十四節気それぞれの具体的な月日と意味を簡単にお伝えしました。
二十四節気は、必ずしも今の季節感を端的に示すものではありません。それでも二十四節気は今でもしっかりと残っています。
たとえば、春夏秋冬の季節の始まりを示す立春・立夏・立秋・立冬。
あるいは、季節の中間を示す春分・夏至・秋分・冬至などは、今でもとても馴染みのある言葉です。
ところで二十四節気は1年を24等分するものですが、365日を24で除しても割り切れる数字にはなりません。
そのため毎年の二十四節気のそれぞれは、必ずしも一定の月日に来るわけではありません。
そのようなことから、この記事では2026年の二十四節気の月日をお伝えしました。
スポンサーリンク
スポンサーリンク