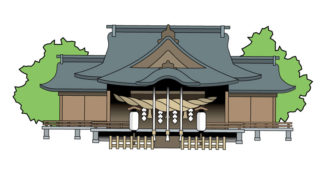2026年の大寒はいつ?時期と季節の風習のいくつかをご紹介します

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
大寒【だいかん】とは
この記事では、2026年(令和8年)の大寒の時期についてお伝えします。また、大寒の時期に行われる風習のいくつかもご紹介していきます。
ところで、大寒とはどのような日なのでしょうか。
日本には二十四節気という季節の分かれ目があります。
二十四節気は、1年を春夏秋冬の4つに分け、さらに季節ごとを細分化し6つに分けます。
春夏秋冬(4)×各季節の細分化(6)で、1年で24の季節の分かれ目が生まれます。
そのため1年の中で節気は、概ね15日ごとに訪れます。
大寒は二十四節気の中の一つです。ちなみに大寒の一つ前の節気は小寒、一つ後の節気は立春になります。
文字から、小寒や大寒には冬のイメージ。立春には春のイメージがあります。
冬の季節には6つの節気がありますが、冬の最後の節気が大寒、大寒の後の立春は春の最初の節気になります。
時期的には、冬から春に移る過程の節気が大寒と思われるかもしれません。
ただ、大寒の文字にはとても寒いという印象があります。立春はあくまでも春の最初の節気です。
大寒は、1年でも一番寒い時期の節気になります。
スポンサーリンク
2026年【令和8年】の大寒はいつ
2026年(令和8年)の大寒はいつでしょうか。実は、大寒には2つの意味があります。
それは、1日だけ指定されている大寒と、ある期間を意味する大寒です。
では、それぞれについて簡単にご紹介します。
1日だけ指定されている大寒
先ほどご案内した通り、1年を24に分ける節気は、ある1日だけを示しています。この場合の大寒は、例年1月20日頃に訪れます。
そして、2026年の大寒も1月20日(火曜日)です。
※ 大寒は年によって月日が変わることがありますが、2017年から2052年までは1月20日になります。
期間を意味する大寒
大寒は、一定の期間を示す場合にも使われています。この場合の期間とは、大寒から立春の前日(節分)までになります。
期間を示す場合の大寒は、1年の中でも最も寒い時期であるということを意味しています。
ところで、この時期によく聞かれる言葉に「寒の内」があります。
寒の内は、大寒の一つ前の節気である小寒から大寒を経て、立春の前日までの約30日。
一方、期間を意味する大寒は、大寒から立春の前日までの約15日。
1年の中で最も寒いといわれる期間を、約30日と広くとったのが寒の内、約15日と狭くとったのが期間を意味する大寒です。
期間を意味する大寒【2026年の場合】
| 大寒 | 2026年1月20日(火曜日) |
| 立春の前日(節分) | 2026年2月3日(火曜日) |
| 立春 | 2026年2月4日(水曜日) |
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
大寒に行われる風習
それでは、大寒の時期に行われる風習のいくつかをご紹介します。寒稽古
大寒の時期で有名なのは寒稽古です。寒い季節なのに、滝にうたれたり、海に入ったりなどがテレビで放映されますが、これらも寒稽古の一つとして行われることが多いようです。
では、寒稽古以外の風習などを次にご紹介します。
大寒みそぎ
大寒みそぎは、大寒の日に滝の水など冷水につかり心身を清める行事です。全国の神社のうち、一部で行われています。
大寒の卵
大寒の卵は、大寒の日に生まれた卵です。一年の中で最も寒い時期に生まれた卵は滋養が豊富と考えられています。
また、大寒の卵は金運や健康運に良い効果があるという言い伝えもあります。
もしかしたら近い将来、大寒の卵がブームになるかもしれないですね。
寒の水
寒の水というのは大寒の日ではなく、寒の内に汲まれた水という意味です。寒い時期の水は、雑菌が少なく水の質も良いと考えられていました。
そこで、地域によっては寒の水を直接に飲むということも行われていたようですが、さらに有名なのは「寒仕込み」です。
「寒の水」で作られたものは長期保存に向いているということで、味噌、醤油、酒などが作られます。
また、凍り豆腐や寒天も知られています。
まとめ

この記事では2026年の大寒はいつということで、大寒はある特定日を指す場合と、一定の期間を示す場合の2つをご紹介しました。
また、それぞれの「いつ」もお伝えしてきました。
大寒には、とても寒いというイメージがありますが実際にそのとおり。大寒の頃になると、長く続く寒さが苦痛になります。
でも、もう少しで立春。
立春で急に暖かくなるわけでもありませんが、その言葉にほっとするのは私だけでしょうか。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク