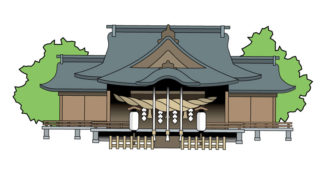土用の丑の日の意味やうなぎを食べるようになった由来をお伝えします

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
土用の丑の日とは
土用の丑の日が近づくと、スーパーなどでうなぎのかば焼きがたくさん並べられます。土用の丑の日にうなぎを食べることが、年中行事のようになっている人もいますが、なぜ土用の丑の日にうなぎを食べるのでしょうか。
そこで、土用の丑の日にはどのような意味があるのか。
また、土用の丑の日にうなぎを食べるのはどんな由来があるのか。
そして、土用の丑の日にうなぎを食べるきっかけになった人物、平賀源内についても簡単にお伝えします。
スポンサーリンク
土用の丑の日の意味
最初に土用の丑の日の意味についてお伝えします。日本の暦には、二十四節気があります。
二十四節気は1年を24に分け、それぞれに季節の移ろいを示す名前をつけたものです。
その二十四節気の中にあるのが、立春・立夏・立秋・立冬です。
「立」には季節の始まりという意味があります。
たとえば立春は、暦の上ではこれから春が始まるという意味です。
そして土用は、それぞれの「立」の前の概ね18日間を指すものとされていました。
立春の場合だと、冬の土用の期間(約18日間)を過ぎると、春(立春)になるというものです。
「立」が季節の始まりだとしたら、その直前の土用は次の季節に少しずつ向かっていく期間になります。
このことからもわかる通り、土用は1年に4回あります。
もっとも近年は、立秋の直前の夏の土用の約18日間を指すことが多いようです。
次に、暦には十二支があてはめられていました。
現在でも、子年(ねずみどし)、寅年(とらどし)というように、それぞれの年に十二支をあてはめていますが、昔は日にも十二支があてはめられていました。
もちろん、丑の日(うしのひ)もその一つ。
夏の土用の期間にある丑の日を、一般的に「土用の丑の日」と称するようになります。土用の期間は約18日。十二支は1周で12日。
したがって、年によっては夏の土用の丑の日が1日だけのこともあれば、2日のこともあります。
なお、2日目の丑の日を「二の丑」と称しています。
このように土用の丑の日は、暦上の規則性に基づく意味はあったものの、土用の丑の日にうなぎを食べるというような意味があったわけではありません。
スポンサーリンク
土用の丑の日にうなぎを食べるようになった由来
立秋の直前の夏の土用は、1年でも最も暑い時期ですが、夏の「土用の丑の日」にうなぎを食べる習慣は、江戸時代に由来すると言われています。土用の丑の日にうなぎを食べるようになった由来としては諸説あるものの、とりわけ有名なのは平賀源内(1728年~1780年)が広めたという説です。
天然うなぎがおいしい時期は晩秋から初冬で、夏のうなぎは痩せていて旬とは言えません。
もちろん、江戸時代に養殖の技術はないので、旬の時期を動かすこともできません。
しかし、これで困るのはうなぎ屋です。
そこで、うなぎ屋は平賀源内に相談します。
平賀源内はうなぎ屋の軒先に「土用の丑の日はうなぎを食べよう」という意味の張り紙を出すよう提案。
実際に張り紙を出したところ人気爆発でうなぎ屋も大繁盛。
平賀源内のセールスプロモーションが成功して、夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が根付いたとされています。
夏の土用の時期は、1年の中でも最も体力を消耗する期間。
夏バテをする季節に、栄養豊富なうなぎを食べて体力を回復する。
夏の土用の季節は、うなぎの旬とは言えなかったものの、平賀源内の提案は理にかなっているような気もします。
さいごに 平賀源内とは
この記事では、土用の丑の日にはどのような意味があるのか。また、土用の丑の日にうなぎを食べる由来についてお伝えしました。
ところで今でも続く、土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣のきっかけを作った平賀源内は、どのような人物だったのでしょうか。
平賀源内は江戸時代中期の人物で、学者・医者・作家・発明家などさまざまな顔を持っていました。
平賀源内で知られているのはエレキテルです。
エレキテルは簡単に言えば発電機のようなもので、外国から入り既に破損していたエレキテルの修理復元に成功しています。
残念なことに、平賀源内は誤って人を殺傷した罪で投獄され、獄中で病死します。
ただ、獄中で亡くなったことには異説もあります。
平賀源内は、絶大な権力を握っていた老中田沼意次(たぬまおきつぐ、1719年~1788年)と懇意でした。
そこで田沼意次は、平賀源内が獄中で亡くなったことにして、秘密裏に匿い天寿を全うさせたとも伝えられています。
平賀源内は稀有な才能を持った人物として知られていましたが、その生涯もミステリアスであったようです。
■合わせて読みたい
⇒ 平賀源内と杉田玄白と田沼意次にまつわるエピソードとは
⇒ 土用の丑の日のうなぎ以外の食べ物は案外たくさんあった!
⇒ うなぎの名前の由来の諸説をまとめて簡単解説します!
⇒ うなぎのうな丼やうな重とひつまぶしの違いをわかりやすく!
⇒ 土用は土いじりをしてはいけないの?年4回の時期もご紹介!
⇒ 養殖ウナギと天然ウナギの違いを大きく4つに分けて簡単解説します!
⇒ うなぎの旬はいつ?天然と養殖では時期に違いがあった
⇒ 8月といえばを行事・祝日・暦・花に分けてお伝えします
スポンサーリンク
スポンサーリンク