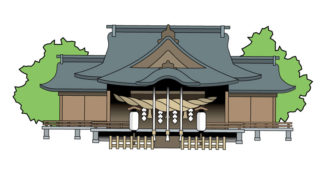1月の花といえば!見頃を迎える11種類をご紹介します

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
目次
1月の花といえば
この記事では、1月の花といえばということで、1月に見頃を迎える花11種類の名前や特徴を簡単にお伝えします。ご紹介するのは、草本類(草)・木本類(木)の順番で、木については花だけでなく実や葉を楽しむものも含めています。
なお、ご紹介するのは関東地方の平野部を基準に考えています。
地域で見頃が異なることもありますが、ご了承ください。
スポンサーリンク
1月の花といえば【草本類・花】
オキザリス
| 分類 | カタバミ科 |
| 見頃 | 10月~4月 |
オキザリスは品種が数百種類もあると言われていて、花の咲く時期も、花の大きさや色も様々にあります。
草丈が低く、丈夫で育てやすいことで人気があります。
シクラメン
| 分類 | サクラソウ科 |
| 見頃 | 11月~4月 |
シクラメンは花期が長く、花の色や花の形も多彩なので人気があります。
ただ冬の寒さは苦手にしているので、ガーデンシクラメンなど一部の品種を除けば屋内で管理します。
また、高温多湿も嫌うので、翌年も同じように花を咲かせるのは難しいと言われています。
プリムラ・オブコニカ

| 分類 | サクラソウ科 |
| 見頃 | 12月~4月 |
また冬の寒さにも弱いため、屋内で花を楽しむのが一般的です。
なお、葉に毒性がありかぶれることがあるものの、最近では毒性のない品種が中心になっています。
プリムラ・ポリアンサ
| 分類 | サクラソウ科 |
| 見頃 | 12月~4月 |
もっとも、冬の寒さには少し弱いため、屋内で楽しむことが多い植物です。
また、プリムラ・ポリアンサは多年草ですが、耐暑性があまりないため一年草で扱われています。
なお、プリムラ・ポリアンサの交配種がプリムラ・ジュリアンで、プリムラ・ポリアンサより一回り小さい花を咲かせるプリムラ・ジュリアンも人気があります。
プリムラ・マラコイデス

| 分類 | サクラソウ科 |
| 見頃 | 12月~3月 |
また、プリムラ・オブコニカやプリムラ・ポリアンサよりは寒さに強いと言われているものの、それでも屋外だと花がしおれてしまうこともあります。
プリムラ・マラコイデスは、小さな花が咲く人気の植物です。
スポンサーリンク
1月の花といえば【木本類・花や実や葉】
アッサムニオイザクラ

| 分類 | アカネ科 |
| 見頃 | 12月~2月 |
ただし、耐寒性があまりないため、冬は日当たりの良い室内で管理して花を楽しみます。
また、夏の暑さにも弱いので、木本類とはいっても一年草として扱うのが一般的です。
アッサムニオイザクラの何よりの特徴は、名前が示すように良い香りがすることです。
なお、アッサムニオイザクラはルクリア、あるいは単にニオイザクラの名前でも販売されています。
センリョウ
| 分類 | センリョウ科 |
| 見頃 | 11月~2月 |
厄除けにつながる赤い実と、千両という名前の縁起の良さから、正月飾りによく利用されています。
また樹高が低く、日当たりが良くなくても実をつけることから、家庭の庭でもよく見かけます。
なお、赤い実だけでなく、黄実のセンリョウもあります。
ポインセチア

| 分類 | トウダイグサ科 |
| 見頃 | 11月~3月 |
また、冬の寒さにもそれほど強くないため、一般的には日当たりの良い室内で管理します。
なお、ポインセチアは赤色が主流ですが、この部分は苞葉で、中心にある黄色い粒のような部分が花になります。
マンリョウ
| 分類 | ヤブコウジ科 |
| 見頃 | 11月~3月 |
センリョウと同じく、赤い実と万両という名前から、正月飾りによく利用されています。
また樹高が低く、日当たりが良くなくても実をつけることもセンリョウに似ています。
センリョウとマンリョウは似ている部分があるものの全く別の植物です。
特に大きな違いは、センリョウの実は小さく葉の上にできるのに対して、マンリョウの実は大きく葉の下にできることです。
なお、赤い実だけでなく、白実のマンリョウもあります。
ユリオプスデージー

| 分類 | キク科 |
| 見頃 | 10月~5月 |
花の色は明るい黄色で、花の形はマーガレットに似ています。
ユリオプスデージーは花期が長く、寒さにも暑さにも強いので屋外で楽しむことができます。
また、管理ができれば毎年花を楽しむこともできます。
屋外でも半年近く花が楽しめるユリオプスデージーは貴重な存在です。
ロウバイ

| 分類 | ロウバイ科 |
| 見頃 | 12月~2月 |
漢字で蝋梅と表記しますが梅の仲間ではなく、花の形が梅に似ていることからこの文字が充てられています。
ロウバイは、ろう細工のような花を咲かせること、冬の寒い時期に明るい黄色い花を咲かせることで人気があります。
ロウバイの品種の中でも、ソシンロウバイや満月ロウバイなどは特に人気があります。
まとめ
1月の花といえばということで、1月に見頃を迎える11種類の花などの名前や特徴を、草と木に分け簡単にお伝えしました。ご紹介した草や木以外でも、1月に花を咲かせるものはたくさんあります。
その中で、この記事では主に花が1月に見頃を迎えるものを中心にご紹介しました。
1月と言えば、1年の中でももっとも寒い時期で、楽しめる花も少なくなりがちですが、屋外だけでなく屋内も含めれば、案外とたくさんの花が楽しめるようです。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク