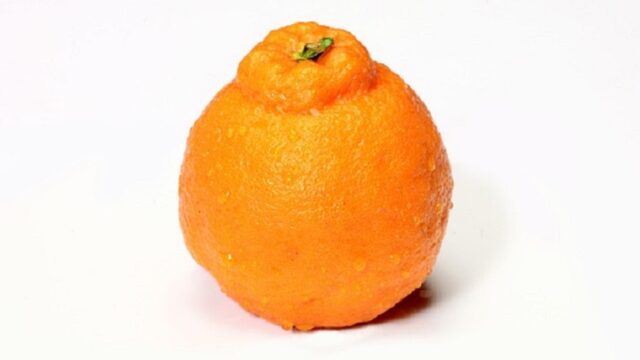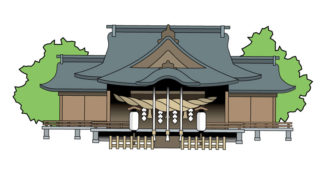ゴールデンウィークはいつから始まったのかを簡単解説!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
目次
ゴールデンウィークとは
この記事では、ゴールデンウィークはいつから始まったのかを簡単にお伝えします。毎年4月下旬から5月上旬にかけての連休は、ゴールデンウィークという名称で定着しています。
日本では暮れから正月にかけて年末年始のお休みがありますが、その後、しばらく大型連休がありません。
それだけに多くの人がゴールデンウィークを待ち望んでいるのではないでしょうか。
ところで、ゴールデンウィークは土曜日や日曜日を含んでの連休の総称ですが、土曜日や日曜日だけでなく、この間にはいくつかの祝日が含まれています。
では、ゴールデンウィークはいつから始まったのでしょうか。
どうやらゴールデンウィークがいつから始まったのかは、由来を知れば答えが出てくるようです。
また、ゴールデンウイ-クにはいくつかの祝日があります。
各祝日はいつから始まったのか、それぞれの祝日にはどのような意味があるのかなども、合わせてお伝えします。
ゴールデンウィークの期間は
まずは、ゴールデンウィークの期間についてお伝えします。ゴールデンウィークの期間についてはいくつかの説があります。
なかには5月3日から5月5日までをゴールデンウィークとする意見もあります。もっとも、これでは3連休にしかなりません。
今では、もう少し長く4月下旬から5月上旬にかけて。土曜日や日曜日を含めての大型連休を一般的にはゴールデンウィークと称しています。
したがって、ゴールデンウィークの期間は毎年異なるという特徴があります。
スポンサーリンク
ゴールデンウィークはいつから始まったの
では、ゴールデンウィークがいつから始まったのかについてご案内します。ゴールデンウィークがいつから始まったのかについては、映画界に由来するというのが定説になっています。
今では、ゴールデンウィークという言葉に慣れ親しんでいますが、ゴールデンウィークは元々「黄金週間」という呼称でした。
この黄金週間という言葉が生まれたのは1951年。当時、庶民の最大の娯楽は映画。映画が多くの人の日常生活に深く関わっていた時代です。
1951年、現在のゴールデンウィークに当たる時期に公開された、獅子文六原作の「自由学校」が、正月やお盆の映画よりもヒットしたことが黄金週間の由来と考えられています。
この映画は、松竹と大映という2つの大きな映画会社がそれぞれに作品を公開していますが、両作品とも興業的には大成功。
そのなかで大映の専務を務めていた松山英夫氏が、この期間を黄金週間と名付けたことに由来すると言われています。
したがって、現在のゴールデンウィークは1951年に生まれたと考えられます。
しかし、黄金週間は語感的に少し古臭いのが難点。そのため黄金週間を英語表記に替えたゴールデンウィークが定着したと考えられています。
なお、黄金週間とゴールデンウィークは同時に生まれた言葉なのか、あるいは黄金週間が先でゴールデンウィークが後に生まれたのか。
このあたりは、はっきりとしていないようです。
今では、ゴールデンウィークという呼び方が一般的です。
ただ、週刊誌ではこの時期に発行されるものを合併号として「黄金週間特別号」「黄金週間合併号」などと称して販売することもあります。
今でも、黄金週間が死語になっていないことが分かります。
ところで、ゴールデンウィークはなじみの深い言葉ですが、NHKや一部のマスコミではゴールデンウィークという言葉を避け、大型連休という言葉を使っているようです。
その理由としては、
・ 連休が1週間とは決まっていないので「ウィーク」では意味をなさない。
・ ゴールデンウィークは民間会社が作った造語である。
・ ゴールデンウィークといっても休めない人もたくさんいる。
などがあるようです。
なお、ゴールデンウィークは映画会社より生まれたというのが定説ですが、ラジオから生まれた、テレビから生まれたという説もあるようです。
この場合の、ゴールデンウイ-クがいつから始まったのかについては定かではありません。
スポンサーリンク
各祝日はいつから始まったの
ゴールデンウィークは、いくつかの祝日と土曜日と日曜日で構成された大型連休です。この配列によって、毎年のゴールデンウィークの期間は異なりますが、その中に含まれる祝日は共通です。
具体的にゴールデンウィークに含まれる祝日としては、
・ 昭和の日 4月29日
・ 憲法記念日 5月3日
・ みどりの日 5月4日
・ こどもの日 5月5日
があります。
それでは、それぞれの祝日がいつから始まったのか、どのような意味があるのを、簡単にご紹介します。
なお、祝日は正式には「国民の祝日に関する法律」により定められた「国民の祝日」で、国民の祝日は休日とする旨が定められています。
言葉としては祝日とも休日とも表記できそうですが、ここでは混乱を避けるために祝日で統一していきたいと思います。
昭和の日 4月29日
昭和の日は、元々昭和天皇の誕生日に由来します。そのため以前の4月29日は、天皇誕生日でした。しかし、昭和64年の昭和天皇崩御に伴い、4月29日の天皇誕生日は「みどりの日」と改められます。
さらに2007年以降、みどりの日は「昭和の日」となり現在に続いています。現在の昭和の日の始まりは2007年になります。
また「みどりの日」は、4月29日から5月4日へ移っています。
現在の昭和の日の意味は、大きな戦争など激動の時代であった昭和を顧みて、将来の日本に思いを馳せる日とされています。
憲法記念日 5月3日
戦前の大日本帝国憲法に代わり、戦後は日本国憲法が現行法になっています。この日本国憲法に由来するのが憲法記念日です。法律にはその法律を発表する公布日と、実施に移す施行日があります。
日本国憲法は1946年11月3日に公布され、その6か月後の1947年5月3日が施行日になっています。
現在、公布された日は文化の日、施行された日は憲法記念日になっています。
憲法記念日という祝日が設けられたのは、1947年5月3日施行日の翌年1948年からになります。
憲法記念日の意味は、日本国憲法の施行を祝うとともに、国の成長を期する日とされています。
みどりの日 5月4日
みどりの日は、前述のとおり2007年に4月29日から5月4日へ移行しています。5月4日が祝日となったことで、それまで曜日の関係で飛び石連休になることもあったゴールデンウィークが、本当に大型連休に成長していったという効果をもたらしています。
みどりの日の意味としては、自然に親しみ自然の恩恵に感謝する、また自然に接して豊かな心を育む日とされています。
こどもの日 5月5日
こどもの日は、端午の節句に由来します。端午の節句は男子の健やかな成長を願う日。そのため、今でも5月5日を迎える前に、デパートなどで五月人形が販売されています。
この端午の節句が、1948年の祝日法により、1949年にこどもの日になっています。
端午の節句は男子の成長を願う日。しかし、現在のこどもの日は男子に限定されるものではありません。
こどもの日の意味は、子供の成長を願うとともに、子供の幸福を図る日とされています。男子だけでなく、子供全体が対象になっています。
また、こどもの日には、母に感謝する日という意味もあるようです。
母に感謝する日は「母の日」と思いがちですが、こどもの日にも母に感謝するという意味が込められているのは驚きです。
さいごに
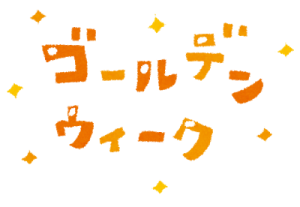
この記事では、ゴールデンウィークはいつから始まったのか。
合わせて、ゴールデンウイ-クの各祝日はいつから始まったのか、それぞれの祝日にはどのような意味があるのかなどもお伝えしてきました。
ゴールデンウィークは、いつからいつまでと厳密に期間が定まっているものではありません。
土曜日や日曜日の位置によって、毎年のゴールデンウィークは前後にずれることはあります。
もっとも、上記のようにゴールデンウィークには4つの祝日が入ります。また、その祝日に土曜日や日曜日が絡んできます。
以前は、ゴールデンウィークといっても実質は飛び石連休。
そんなことも多かったようですが、現在のゴールデンウィークは大型連休になる可能性が格段に上がっています。
果たして今年のゴールデンウィークはいつからいつまでになるのでしょうか。何れにしても早めに予定を立てておきたいですね。
なお、現在ではあまり意識されてませんが「立夏」や「八十八夜」もゴールデンウィークの頃に訪れます。
■合わせて読みたい
⇒ ゴールデンウィークが見頃の花を関東・関西など地域別にご紹介
⇒ 5月といえばを花・祝日・行事・暦・天気に分けお伝えします
⇒ 祝日を一覧でご案内します!
⇒ 立夏の時期と決まり方や意味をご紹介します!
⇒ 八十八夜はいつ?意味やお茶との関係もご案内します
スポンサーリンク
スポンサーリンク