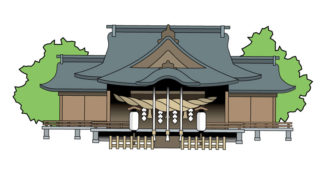七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜ?歴史的由来や経済的理由とは

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜ
日本ではそれほど馴染みはありませんが、欧米ではクリスマスに七面鳥を食べる習慣が根づいています。この記事では、七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜなのか、その歴史的由来や経済的理由についてご紹介します。
また、日本でクリスマスに七面鳥を食べる習慣がなぜ一般的ではないのか、その理由についても簡単にお伝えします。
スポンサーリンク
七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜ 歴史的由来
七面鳥は、アメリカやカナダ南部など北アメリカ原産の鳥です。野生の七面鳥は家畜化され、16世紀になるとスペインやイギリスに持ち込まれます。
たとえば、イギリスではヘンリー8世(1509年~1547年)がクリスマスに七面鳥を食べたとされ、当時の王族の間にも広まったと言われています。
17世紀になると、イギリスからアメリカへ移住が行われるようになりますが、そこで直面したのが深刻な食糧難でした。
その際、アメリカの先住民族が七面鳥などの食料を分け与えたことで、移住した人々は飢えをしのぐことができます。
そして、移住した人々が農作業に携わり農作物を収穫した際に、収穫に感謝する「感謝祭(サンクスギビング)」を祝うようになり、そのごちそうとしてふるまわれたのが七面鳥です。
感謝祭は、毎年11月の第4木曜日に祝われ、七面鳥はお祝いの象徴とも言われていますが、後には感謝祭だけでなくクリスマスディナーのメイン料理としても七面鳥が振る舞われるようになったと考えられています。
また、イギリスの小説家チャールズ・ディケンズ(1812年~1870年)が、1843年に発表した小説に「クリスマス・キャロル」があります。
クリスマス・キャロルは、守銭奴で冷酷な初老の商人スクルージが主人公で、事務員のクラチットを薄給で雇っていました。
クリスマスの前に、クラチットはクリスマスの休暇を求めますが、スクルージは休暇は認めるが翌日は早く出勤するよう伝えます。
また、クリスマスを前に寄付を募りにきた人々にも、冷たく対応し追い返してしまいます。
クリスマスが嫌いなスクルージでしたが、そこに現れたのが既に亡くなっていた旧友の亡霊です。
亡霊に諭されたスクルージは改心。
スクルージは、薄給で貧しい生活を送っていたクラチット一家に七面鳥を贈ります。
この描写により、クリスマスに七面鳥を食べることが広く認識され、中流以上の多くの家庭での習慣になったと考えられています。
スポンサーリンク
七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜ 経済的理由
現在でも、クリスマスに七面鳥を食べる習慣は欧米諸国を中心に広くあります。七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜなのか。
そこには歴史的由来だけでなく、経済的理由もあるようです。
感謝祭は収穫を祝う日、クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う日で、何れも家族や友人など多くの人が集まります。
七面鳥以外で食べられるものとしては、ガチョウや白鳥などかあります。
しかし、七面鳥はガチョウや白鳥よりもずっと大きく、1羽でもクリスマスなどで十分な量の肉を提供することができます。
またガチョウや白鳥に比べると、七面鳥は飼育が容易でコスト面で優位だったという点も、クリスマスに七面鳥という習慣を後押ししたようです。
そうした経済的なことも、七面鳥がクリスマスの定番料理として定着している理由になっているようです。
また、牛肉や豚肉などは日常的に食べられているのに対して、七面鳥は感謝祭やクリスマスなど、特別の日にしか食べる機会がありません。
こうした非日常感も、七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜなのかの理由の一つになっているのかもしれません。
日本でクリスマスに七面鳥を食べるのが一般的でない理由

この記事では、七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜなのか、その歴史的由来や経済的理由についてご紹介しました。
ところで、七面鳥がクリスマスの定番料理となっている国は多数あるものの、日本でクリスマスに七面鳥を食べる習慣は一般的でないようです。
なぜなのか。
最後に、日本でクリスマスに七面鳥を食べる習慣が一般的でないのはなぜなのかについて、簡単に触れておきたいと思います。
まず現在に至るまで、日本では七面鳥を食べる習慣が根づいていないため、輸入されることも生産されることも少ないことがあげられます。
また七面鳥はサイズが大きいため、家庭ではオーブンに入れて焼くことができないなど、調理のハードルが高いことも考えられます。
さらに、欧米などで七面鳥は伝統料理として感謝祭やクリスマスに使われているものの、日本は伝統ではなくイベント的な意味合いが強いことも影響しているのかもしれません。
そして、七面鳥の代わりに日本で一般化したのがチキンです。
チキンは、流通量も多く入手が簡単、大きさも調理しやすいサイズであることから、七面鳥ではなくチキンがクリスマスの食卓の主役になっています。
■合わせて読みたい
⇒ クリスマスの意味や由来とは!さまざまな風習も簡単にお伝えします
⇒ クリスマスイブとクリスマスの違いとは!どっちが大切なのかもご紹介
⇒ クリスマスにチキンを食べるのはなぜ?日本独特の理由をご紹介!
⇒ クリスマスの花は赤と緑と白が主役!5種類を簡単にご紹介します
⇒ クリスマスプレゼントの花でおすすめの6種類とその理由とは!
⇒ クリスマスツリーの意味とは!起源から現在まで簡単にお伝えします
⇒ クリスマスツリーの飾りの意味とは!10種類を簡単解説します
⇒ クリスマスリースの意味をわかりやすく様々な視点からお伝えします!
⇒ クリスマスキャロルの意味とは!歌う時期や代表曲などもお伝えします
⇒ クリスマスマーケットの歴史や意味をわかりやすくお伝えします!
スポンサーリンク
スポンサーリンク