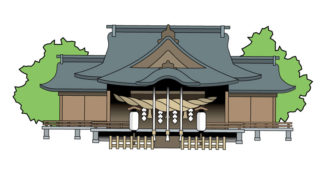クリスマスの意味や由来とは!さまざまな風習も簡単にお伝えします

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
クリスマスの意味や由来とは
クリスマスになると、華やかなイルミネーションを眺め、豪華なディナーやプレゼント交換を楽しむ人が多くなります。ところで、クリスマスはどのような日なのでしょうか。
どうやらクリスマスには深い意味があるようです。
この記事では、クリスマスの意味や由来、あわせてクリスマスのさまざまな風習の由来について簡単にお伝えします。
スポンサーリンク
クリスマスの意味
クリスマスの意味は、英語で考えるとわかりやすくなります。クリスマスは英語表記で「Christmas」。
Christmasは、Christ(キリスト)とMass(ミサ)を合わせた言葉です。
ミサは礼拝という意味なので、クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う「降誕祭」で、キリスト教における最も重要な祝祭の一つになります。
スポンサーリンク
クリスマスの由来
クリスマスの意味では、クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う「降誕祭」だとお伝えしました。では、イエス・キリストが誕生したのは12月25日なのでしょうか。
実は、イエス・キリストが誕生した日は諸説ありはっきりしていませんが、春から秋というのが有力で、冬ではないと考えられています。
したがって、12月25日のクリスマスはイエス・キリストが生まれた日ではないとされています。
どうやら、クリスマスはイエス・キリストの誕生した日に由来するものではないようです。
では、どうして12月25日がクリスマスになったのでしょうか。
これについても複数の説があるようですが、ここではその中で有力とされている説をご紹介します。
12月25日は、1年でもっとも昼の時間が短い冬至の直後です。
ローマ帝国では、冬至は太陽の力が再び強まる始まりの日で、太陽神を讃える冬至祭が行われていました。
ローマ帝国の太陽神を崇拝する冬至祭に、イエス・キリストを世の光と見立てて融合させたのが、クリスマスの由来と考えられています。
4世紀のローマでは、12月25日を降誕祭として制定しています。
どうやら12月25日のクリスマスは、イエス・キリストが誕生した日ではなく、イエス・キリストがこの世に誕生したことをお祝いする日のようです。
クリスマスの様々な風習の由来

ここまで、クリスマスの意味や由来についてお伝えしました。
ところで、クリスマスには様々な風習があります。
この記事の最後に、いくつかのクリスマスの風習を取り上げ、その由来を簡単にご紹介します。
クリスマスツリーの由来
クリスマスには、クリスマスツリーがつきものです。クリスマスツリーは、16世紀のドイツを起源とする説が有力です。
クリスマスツリーに使われるのはもみの木。
冬でも葉を落とさない常緑樹のもみの木は、永遠の命や希望の象徴とされ、クリスマスツリーという風習が生まれました。
サンタクロースの由来
サンタクロースは、4世紀にトルコに実在したキリスト教司教「聖ニコラウス」がモデルと言われています。聖ニコラウスは貧しい人や子どもたちに、夜中にこっそりと贈り物をしていたという逸話が残っています。
サンタクロースは、オランダではシンタクラースと呼ばれていましたが、その後は英語のサンタクロースに変化したと考えられています。
なお、サンタクロースの贈り物といえば靴下が定番です。
これは、聖ニコラウスが貧しい家の煙突から金貨を投げ入れたところ、暖炉の近くにあった乾かしていた靴下の中に金貨が入ったという伝説に由来しています。
クリスマスプレゼントの由来
クリスマスプレゼントは、前述のサンタクロースの伝説が由来になっています。それ以外のクリスマスプレゼントの由来としては、東方の三博士がイエス・キリストの誕生時に、金・乳香・没薬の贈り物を持ってイエス・キリストを訪ね、拝んだとされる聖書の記述に由来するという説もあります。
■合わせて読みたい
⇒ クリスマスイブとクリスマスの違いとは!どっちが大切なのかもご紹介
⇒ クリスマスの花は赤と緑と白が主役!5種類を簡単にご紹介します
⇒ クリスマスプレゼントの花でおすすめの6種類とその理由とは!
⇒ クリスマスリースの意味をわかりやすく様々な視点からお伝えします!
⇒ クリスマスツリーの意味とは!起源から現在まで簡単にお伝えします
⇒ クリスマスツリーの飾りの意味とは!10種類を簡単解説します
⇒ クリスマスキャロルの意味とは!歌う時期や代表曲などもお伝えします
⇒ クリスマスマーケットの歴史や意味をわかりやすくお伝えします!
⇒ 七面鳥をクリスマスに食べるのはなぜ?歴史的由来や経済的理由とは
⇒ クリスマスにチキンを食べるのはなぜ?日本独特の理由をご紹介!
スポンサーリンク
スポンサーリンク