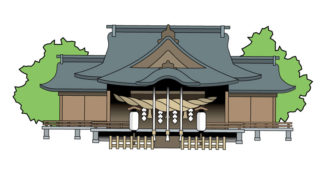2026年の正月事始めはいつでどんなことをする日なのかをご案内?

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
2026年(令和8年)の正月事始めはいつ?
この記事では、正月事始めについてご案内します。正月事始めは、「正月ことはじめ」と表記されることがあります。
また、正月事始めを省略して、単に「事始め」または「ことはじめ」と表記されることもあります。
では、正月事始めの日はいつになるのでしょうか。正月事始めの日は、毎年一定の時期で曜日は関係ありません。
正月事始めの日は、毎年12月13日。
したがって、
2026年の正月事始めの日は、2026年(令和8年)12月13日(日曜日)になります。
では、正月事始めにはどんな意味があるのか。
そしてどんなことを行うのか、簡単にご案内します。
スポンサーリンク
正月事始めの意味とは
事始めではイメージとしては弱いものがあります。しかし正月事始めと言われれば、正月事始めは正月に何か縁のある行事であることが推測できます。
では、正月事始めには、どのような意味があるのでしょうか。
正月事始めの日は、本格的に正月の準備をするスタートの日とされています。
したがって、正月事始めは実際の正月より前になければいけない。それが、正月事始めの日を12月13日にしているようです。
正月を迎えるためには相応な準備が必要。そのため正月事始めの日は、正月よりもかなり早い時期になっています。
正月事始めの行事とは

正月事始めの日は、正月の準備をするスタートの日です。
では、正月事始めでは具体的にどんなことをするのでしょうか。
正月事始めで行う行事の代表例としては、煤払い(すすはらい)と松迎えがあります。
スポンサーリンク
煤払い(すすはらい)とは
煤払いは、簡単に言えば年末の大掃除です。屋内の天井や壁にたまった煤の掃除をすることから煤払いと言われています。また屋内と書きましたが、それは居住スペースに限らず、家の中の神棚や仏壇も清めることを意味しています。
日本には、年神様(としがみさま)という考えがあります。
年神様は元旦になると高い山から下りてきて、家に1年の幸せをもたらすというものですが、年神様をお迎えするために煤払いをします。
そう考えると、煤払いは単に年末の大掃除というだけでなく神聖なもの。煤払いには、年神様を迎えるための神事という意味もあるようです。
なお、年神様は歳神様、歳徳神(としとくじん)と表されることもあります。
松迎えとは
松迎えは、正月の門松を用意するために恵方の山に松を伐りに行く日。そして、正月のお雑煮を作るための薪を取りに行く日という意味があります。
門松は年神様を迎えるために必要なものと考えられています。
年神様が家にやってくるとき、まずは目印が必要です。また、松の木は神聖なものと考えられていました。
そのため松迎えで松を用意して、煤払いが終った後に門松の用意をする。
これが一般的な正月準備の順番となっていたようです。
また、正月には餅がつきものです。
正月事始めの行事として、この記事では煤払いと松迎えをご案内してきましたが、餅つきも正月事始めの行事の一つとされています。
正月事始めの日以降に餅をつき、正月にお雑煮にして食べる。
お雑煮を作るのには火が必要です。そのため松迎えの時に、そのための薪を用意しておく。
これも正月事始めの行事としては重要な意味を持っていました。
■合わせて読みたい
⇒ しめ飾りはいつからいつまで飾るものなの
⇒ 正月の花はいつまで飾るのかは意味が分かれば答えもわかる
⇒ 正月三が日は掃除をしてはいけない2つの理由を簡単解説
⇒ 正月に餅を食べるのはなぜ?歴史を遡ってお伝えします
⇒ 正月の雑煮の意味を歴史をさかのぼってお伝えします!
さいごに

この記事では、12月13日が正月事始めの日であること。
そして、2026年(令和8年)の正月事始めの日は、2026年12月13日(日曜日)になることをお伝えしました。
また、正月事始めにはどんなことをするのかということで、煤払いと松迎えのご案内をしました。
正月事始めについて考えると、関西地方ではもう一つの行事があるとされています。
それがお歳暮です。
関東地方の場合、お歳暮を贈る時期は12月初旬からとされています。それに対して関西地方はもう少し遅く12月13日以降。
つまり、正月事始めの日以降にお歳暮を贈るとされています。
特に関東から関西にお歳暮を贈るような場合は、少し注意が必要かもしれないですね。
■合わせて読みたい
⇒ お歳暮の時期の関東と関西の違いとは!いつからいつまでを簡単解説
⇒ 初詣は神社とお寺のどっちに行けばいいのかを簡単解説!
⇒ 12月といえばを行事・暦・花に分けてお伝えします!
正月事始めと勘違いされやすい小正月は、次の記事をご覧ください。
⇒ 小正月はいつ?意味や行事も簡単にお伝えします
スポンサーリンク
スポンサーリンク