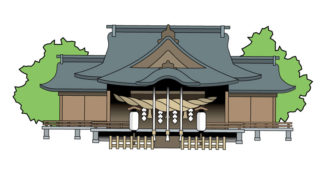なぜ正月に餅を食べるのかを歴史を遡ってお伝えします!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
はじめに
今では、餅は1年を通して買うことができます。しかし長い間、餅は正月に食べる特別な食べ物とされてきました。この記事では、正月に餅を食べるのはなぜなのかを、歴史を遡ってお伝えします。
なお、正月に餅を食べるのはなぜなのかについては様々な意見があるようです。ここでは、その中でも多く聞かれる意見をご紹介します。
スポンサーリンク
平安時代の歯固めの儀
餅がいつ生まれたのかは定かでありませんが、奈良時代初期には餅の記述が残っています。平安時代に入ると、餅は正月の宮中の儀式である「歯固めの儀」に使われるようになります。
中国から伝わった歯固めの儀は、堅い餅を噛みしめて歯を強くするというもので、健康祈願につながっていました。
また、餅は伸びて切れないということで、歯固めの儀は長寿祈願の意味も込められた行事だったと考えられています。
もっとも餅は貴重で、「ハレの日」という特別な日に神さまに捧げるものとされていました。
歯固めの儀の餅は、正月という特別な日に家にやってくる神さまに捧げ、神棚にお供えした餅を降ろし儀式で使うものであったようです。
スポンサーリンク
正月に餅を食べるのはなぜ
正月になると、家に年神様が訪れます。年神様は稲作の神さまとされ、春から秋までは水田にいて、その年の豊作をもたらします。
そして、正月を迎えると各家庭を訪れます。
年神様は稲作の神なので、各家庭では稲わらで作った正月飾りで迎えます。
家にやってきた年神様は神棚にある餅に宿ります。
そして、人々がその餅を食べることで、その年の豊作や家族の健康をいただけると言われるようになりました。
正月に餅を食べるのはなぜなのか。
そもそも餅は貴重だったので、いつでも食べられるわけではありませんでした。
大切な餅を、1年の始まりの正月に食べることでその年を無事に過ごせる。
そうした人々の願いが今に伝わっているようです。
鎌倉時代の鏡餅
神さまにお供えしていた餅は、元々は平べったい円形の丸餅であったようです。これが、ふっくらとした丸鏡の形「鏡餅」になったのは、鎌倉あるいは室町時代のこととされています。
当時、丸い鏡には神様が宿り、霊力を持つと信じられていました。
そこで丸鏡に似せることで、餅に年神様が宿るとも考えられていたようです。
もっとも、鏡餅が生まれても丸餅がなくなったわけではありません。
今でも、正月には子供たちにお年玉が配られますが、元々はお金ではなく餅。
正月に子供に丸い形の餅を配ったものが、お年玉の由来とされています。
まとめ
この記事では、なぜ正月に餅を食べるのかを歴史を遡ってお伝えしました。正月に餅を食べるのは、年神様の存在が大きく関係していたようです。
しかし、実生活に即して考えると、まったく別の意味も見えてきます。
昔は12月13日の「正月事始め」の日以降に、大掃除や正月の準備を行うものとされていました。
正月の準備は今よりもずっと大変なもので、多くの作業は女性が担ってきました。
正月を迎えたら、正月準備だけでなく台所仕事に追われていた女性に休息が必要です。
正月に台所仕事などをしないで済むようにと考えられたのが、おせち料理であり、保存がきく餅でした。
正月の餅に意味があるのと同じように、おせち料理も一つ一つの具材に意味が込められていますが、最大の目的は女性を休まさせるため。
儀式も神様も否定はできませんが、正月に餅を食べるのはなぜなのかについては、実生活に即した意味合いも大きかったのではないでしょうか。
■合わせて読みたい
⇒ 正月事始めはいつ?どんなことをする日なの
⇒ 正月の餅つきの由来やいつ行うのかをわかりやすくお伝えします!
⇒ 正月の雑煮の意味を歴史をさかのぼってお伝えします!
⇒ おせち料理の意味を一覧で!30種類の具材を大公開します
スポンサーリンク
スポンサーリンク