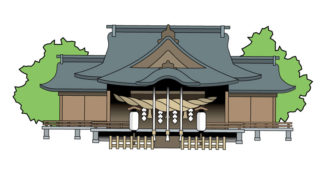豊臣秀長ゆかりの地8つの場所とそれぞれの関わり合いをお伝えします

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
目次
豊臣秀長とは
この記事では、豊臣秀長ゆかりの地8つの場所と、それぞれの場所と豊臣秀長の関わり合いについてお伝えします。ところで、豊臣秀長とはどのような人物だったのでしょうか。
豊臣秀長(1540年~1591年)は、豊臣秀吉(1537年~1598年)の弟で、生まれは兄豊臣秀吉と同じ尾張国中村です。
その後、織田信長の家臣となった豊臣秀吉が出世の糸口をつかんだ、1566年の墨俣一夜城建設の頃に、兄豊臣秀吉とともに織田信長の家臣になります。
そして兄豊臣秀吉に従い、各地を転戦。
織田信長が本能寺の変で倒れた後も、豊臣秀吉のもとで四国・九州などの平定に貢献。
特に1585年の四国征伐では総大将を務め、四国平定後は大和・紀伊・和泉・河内の一部を与えられ約100万石の大名となり、大和郡山城を居城とします。
豊臣秀長は領国経営にも優れた手腕を発揮し、豊臣政権にあっては兄豊臣秀吉の暴走を諫める貴重な存在で、1587年には権大納言に任官され「大和大納言」と称されています。
しかし病魔に侵され、1591年に豊臣秀長は郡山城で死去。
豊臣秀長の死により豊臣秀吉を諫める人物はいなくなり、豊臣政権がぐらつきをみせる中にあって、1598年には豊臣秀吉も病死。
そして1600年の関ヶ原の戦いで豊臣家は政治の実権を失い、さらに1616年の大坂夏の陣で豊臣家は滅亡します。
豊臣秀長は、豊臣政権安定のためには必要不可欠な人物であり、早すぎる死が豊臣政権の衰退の原因の一つになったともいわれています。
それでは、豊臣秀長ゆかりの地8つの場所と、それぞれの場所と豊臣秀長の関わり合いをお伝えします。
スポンサーリンク
豊臣秀長ゆかりの地 尾張国中村

豊臣秀吉が生まれたのは1537年、その3年後に豊臣秀長は生まれています。
生まれた地は何れも尾張国中村。
豊臣秀長がいつまで中村にいたのかははっきりとしていませんが、この地で幼少期を過ごしたものと考えられます。
なお、豊臣秀吉が生まれた場所は中村公園になっていて、園内には豊国神社や名古屋市秀吉清正記念館などがあります。
中村公園 愛知県名古屋市中村区中村町高畑68ほか
スポンサーリンク
豊臣秀長ゆかりの地 墨俣城
美濃国を攻略するため、織田信長が豊臣秀吉に命じて造らせたのが墨俣城です。豊臣秀吉はごく短期間で築城をしたことから、墨俣一夜城とも呼ばれています。
1566年の墨俣城築城により美濃侵攻が可能になり、豊臣秀吉は築城をきっかけに出世のスピードをあげていきます。
もっとも、墨俣城が築城された年は明らかでなく、城の規模も明確ではありません。
豊臣秀長が豊臣秀吉のもとで働くようになった時期も定かではありませんが、墨俣城築城に際して築城や兵站に携わったとも考えられています。
なお、墨俣城跡の一部は公園として整備されていて、園内には鉄筋コンクリート造の摸擬天守が造られ、内部は大垣市墨俣歴史資料館になっています。
大垣市墨俣歴史資料館 岐阜県大垣市墨俣町墨俣1742-1
豊臣秀長ゆかりの地 長浜城

1573年、浅井氏が滅亡しますが、その功績により豊臣秀吉に旧浅井領が与えられます。
そこで豊臣秀吉はそれまでの今浜という地名を長浜に改めて築城したのが長浜城です。
長浜城では豊臣秀吉が不在の時などに、豊臣秀長が城代を務めることもあったと言われています。
長浜城は1615年に廃城、現在は鉄筋コンクリート造の復興天守が造られ、長浜城歴史博物館になっています。
また、復興天守を含む豊公園は桜の名所としても知られています。
長浜城歴史博物館 滋賀県長浜市公園町10-10
豊臣秀長ゆかりの地 竹田城
織田信長により中国攻めの総司令官に任命された豊臣秀吉に従い、豊臣秀長も但馬国の平定に向かいます。そして1577年、竹田城が落城するとともに、豊臣秀長は城代に任命されます。
その後、1578年に敵に一時奪われるものの、1580年に奪還しています。
江戸時代に入り竹田城は廃城となりますが、石垣などの遺構は残っています。
山城である竹田城は霧により霞んで見えることが多いため、「日本のマチュピチュ」「天空の城」ということで観光客に人気の場所になっています。
竹田城 兵庫県朝来市和田山町竹田
豊臣秀長ゆかりの地 姫路城
1582年の本能寺の変で明智光秀により織田信長が横死、山崎の合戦で明智光秀を破った豊臣秀吉は、翌1583年織田家で豊臣秀吉の最大のライバルであった柴田勝家を賤ヶ岳の戦いで破ります。明智光秀を倒した本能寺の変、柴田勝家を倒した賤ヶ岳の戦いでも功績があった豊臣秀長は、但馬国と播磨国の2ヶ国を拝領します。
このときに豊臣秀長が居城としたのが姫路城と言われています。
1346年に築城された姫路城は小規模なものでしたが、豊臣氏の時代に拡張、さらに江戸時代に入り大幅な拡張が行われています。
江戸時代初期に造られた建造物は、多くが国宝や重要文化財に指定され、日本100名城にも選定されています。
姫路城 兵庫県姫路市本町68
豊臣秀長ゆかりの地 和歌山城

1585年、豊臣秀吉は紀州征伐に乗り出し、豊臣秀長は副将に任じられます。
紀州征伐後、功績があった豊臣秀長には、但馬国・播磨国に代わり、紀伊国・和泉国など約64万石が与えられます。
豊臣秀長が領国経営のため、藤堂高虎に命じて造らせたのが和歌山城です。
和歌山城はその後も城主が変わりますが、豊臣家滅亡後は紀州徳川家が居城として明治維新を迎えます。
現在、和歌山城があった場所には石垣などの遺構が残り、国の重要文化財などに指定されています。
また敷地内には和歌山城公園など数多くの施設があります。
和歌山城 和歌山県和歌山市一番丁
豊臣秀長ゆかりの地 郡山城
1585年、病気で出陣できない豊臣秀吉に代わり、総大将として四国攻めにとりかかります。四国攻めで長宗我部元親を降伏に追い込んだ豊臣秀長は、紀伊国・和泉国に加え大和国を加増されています。
そこで、豊臣秀長が居城としたのが郡山城で、和歌山城には城代をおいています。
郡山城はそれ以前にもありましたが、豊臣秀長が大規模な改修を加え、亡くなるまで居城としています。
その後の郡山城は、城主は変わるものの、江戸時代を経て明治時代になり廃城となっています。
現在は石垣などの遺構が残るほか、桜の名所としても知られています。
郡山城 奈良県大和郡山市城内町
豊臣秀長ゆかりの地 大和郡山市
豊臣秀長は1585年から亡くなる1591年まで郡山城を居城としています。そのため、郡山城があった大和郡山市には、豊臣秀長ゆかりの地がいくつもあります。
大納言塚(奈良県大和郡山市箕山町14)は、豊臣秀長死後に墓所になった場所で、大和郡山市の指定文化財になっています。
春岳院(奈良県大和郡山市新中町2)は、豊臣秀長の菩提寺で位牌や肖像画などが残っています。
洞泉寺(奈良県大和郡山市洞泉寺町15 )は、豊臣秀長が建立したと伝わる寺院で、民衆の病気平癒のため光明皇后が彫ったとされる石地蔵「垢かき地蔵」が知られています。
郡山八幡神社は元は郡山城の場所にありましたが、豊臣秀長が郡山城築城の際に現在の場所に遷座させたと言われていて、近年では野球少年が必勝祈願に訪れる「グラブ神社」としても知られています。
まとめ
豊臣秀長は50歳で短い生涯を閉じています。しかし、豊臣秀吉の弟として活躍したため、この記事でお伝えした場所を含め数多くのゆかりの地があります。
それだけ、豊臣秀長は豊臣政権安定のためには必要不可欠な人物であったと言えるのではないでしょうか。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク