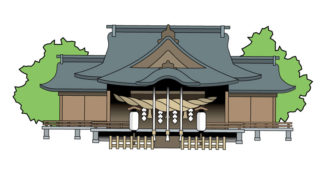正月の餅つきの由来やいつ行うのかをわかりやすくお伝えします!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
正月の餅つき
正月にお餅を食べる人も多いのではないでしょうか。この記事では、正月の餅つきの由来や、餅つきをいつ行うのかをわかりやすくお伝えします。
最近では、餅を食べなかったり、食べるにしてもスーパーなどで購入することが圧倒的に多いかもしれません。
しかし中には、臼や杵を使った餅つきではなく、機械でお餅を作る人もいるようです。
餅つきではなく、機械でお餅を作る方にとっても、特に正月のお餅をいつ作るのかについては参考になるのではないでしょうか。
スポンサーリンク
正月の餅つきの由来
正月の準備のための餅つきは、既に平安時代に行事として定着していたと考えられています。それでは、なぜ餅つきをするのか。
その由来をいくつかご紹介します。
稲作文化との結びつき
餅つきは、稲作信仰に由来すると考えられています。日本では稲は神聖な作物とされ、稲から取れる米を蒸してつき固めた餅には、稲の霊力が凝縮され強い生命力が宿ると信じられていました。
歳神さまへのお供え
正月になると「歳神(としがみ)さま」が各家庭を訪れると考えられていました。歳神さまは正月に訪れ、一年の福や豊作をもたらす神とされています。
その歳神さまを迎えるため、お供え物にしたのが鏡餅です。
人々はお供えした鏡餅を食べることで、神様からの力を授かり、長寿や健康を願ったとされています。
共同体の絆づくり
今では少なくなりましたが、餅つきは家族や近所の人々が集まり行うのが一般的でした。多くの人が集まり力を合わせて餅つきをすることは、新しい年を迎えるための儀式であり、絆を深める役割を果たすと考えられていました。
共同で餅つきをすることで、家族や地域の人々の絆を深めるとともに、一年の無病息災を願ったとされています。
語呂合わせ
餅つきは、望月(もちづき)と語呂合わせができます。望月は満月のことで、望月は満たされるということで、縁起が良いという意味が込められています。
スポンサーリンク
正月の餅つきはいつ行うの
正月になると餅を食べることが多くなります。では、餅を作る餅つきはいつ行うのでしょうか。
餅つきをする時期は、地域や家庭によっても異なります。
たとえば、家族や親戚が集まる正月三が日に行うことや、地域によっては新しい年を迎えてからの「どんど焼き」「左義長」などの行事と合わせて餅つきを行うこともあるようです。
ただ一般的にもっとも多いのは年末。
年末に餅つきを行うことで、正月に歳神さまにお供えする新鮮な鏡餅を準備することができます。
では、年末であればいつでも良いのでしょうか。
こちらについても、餅つきに適した日と、餅つきを避けるべき日があるようです。
年末の中で餅つきに適した日としては、12月28日があります。
この中で8については、「八」の字が末広がりで縁起が良いとされています。
一方、餅つきを避けるべき日としては、12月29日と12月31日があります。
29日は「二重苦」と読めるため不吉とされています。
また31日は、お供えする鏡餅が正月を迎える直前の「一夜飾り」となります。
一夜飾りは葬儀を連想させるため、歳神様にお供えするのは失礼だという考えがあります。
年末の中で餅つきにもっとも適した日は12月28日、また12月29日と12月31日の間の12月30日に行うのも、新鮮な餅をお供えするという意味で差支えないようです。
一方、餅つきを避ける日は12月29日と12月31日。
ただし、12月29日は「二重苦」ではなく「福」につながると考える地域もあるようです。
まとめ

この記事では、正月の餅つきの由来や、いつ行うのかをわかりやすくお伝えしました。
最近では、家庭や地域で餅つきを行うことも少なくなっていますが、餅つきは単なる年末の行事ではなく、さまざまな願いや意味が込められているようです。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク