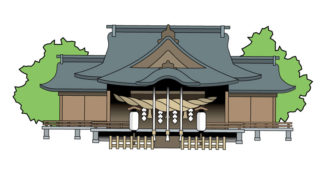重陽の節句の食べ物は菊と栗!意味も合わせてご紹介します

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
はじめに
この記事では、重陽の節句の食べ物と重陽の節句の意味についてご紹介します。まず、節句の意味、五節句の意味、重陽の節句の意味をお伝えし、その後に重陽の節句の食べ物についてご案内をします。
どうやら、重陽の節句の食べ物は「菊」と「栗」がキーワードになるようです。
節句の意味とは
節句には、どのような意味があるのでしょうか。節句の「節」には季節の変わり目という意味があります。
また、季節の筋目である節には、無病息災、豊作、子孫繁栄などを願うという習慣があります。
そして、現在は「句」の字を用いますが、元々は「供」という字を使っていました。
供は「そなえ」と読み、お供え物をするという意味があります。
節供が転じて節句。
そして節句には、季節の変り目に神様にお供え物をして邪気を払い、無病息災、豊作、子孫繁栄を願うという意味があります。
スポンサーリンク
五節句の意味とは
節句は季節の変わり目と書きましたが、節句は1年の中で5つあり五節句と称しています。五節句を順番に挙げると、
| 月日 | 節句の名前 | 別の呼び方 |
| 1月7日 | 人日(じんじつ)の節句 | 七草の節句 |
| 3月3日 | 上巳(じょうし)の節句 | 桃の節句 |
| 5月5日 | 端午(たんご)の節句 | 菖蒲の節句 |
| 7月7日 | 七夕(たなばた)の節句 | 笹の節句 |
| 9月9日 | 重陽(ちょうよう)の節句 | 菊の節句・栗の節句 |
ところで、五節句は奇数月で月と日が同じ数になっています。
その理由については諸説あるようですが、中国で奇数は「陽の数」として縁起が良い数とされていたということ。
さらに「陽の数」が重なるとさらに縁起が良いというのが多く聞かれる意見です。
五節句には1月1日と11月11日が入っていません。
1月1日が五節句に入っていないのは、陽の字が重なるとはいっても1月1日は格別の日。そこで、1月1日は外して1月7日を節句としています。
また、11月11日が入っていないのは、五節句を制度として定めた江戸幕府が、節句を制定するとき奇数でも1桁の数字を前提としたため、11月は除かれたものと考えられています。
なお、江戸幕府は五節句を式日(しきじつ)に定めていましたが、式日の制度は明治6年に廃止されています。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
重陽の節句の意味とは
9月9日は重陽の節句です。節句は陽の数を重ねたものですが、特に一番大きな数字である9は陽の数の極と考えられていました。
陽の数の極である9が重なることから、9月9日を重陽。
そして、重陽の節句は陽の極が2つ重なることから、とてもめでたい日とされていました。
重陽の節句の食べ物とは

重陽の節句は、菊の節句あるいは栗の節句といわれることもあります。
どうしてでしょうか。
奈良時代あるいは平安時代の初期の頃より宮中では観菊の宴が催され、合わせて菊酒(菊の花びらを浮かべたお酒)などが振舞われました。
そのことが語源となlり、重陽の節句は菊の節句と称されるようになっています。
菊には邪気を祓う効果があるとされていて、菊酒を飲むと邪気を払い長命がかなえられると考えられていました。
また、その後は菊酒だけでなく菊のおひたし、菊の和え物などの菊料理も食べられるようになっています。
そして食べ物ではありませんが、重陽の節句には菊湯につかる。あるいは、菊の花を活けるなども重陽の節句の風習として知られています。
菊の節句は宮中より始まりましたが、民衆の間では菊ではなく栗の節句として知られています。
重陽の節句の時期は、ちょうど栗の収穫時期にあたります。
そこで、民間では重陽の節句に栗ご飯を炊くということが行われていますし、栗きんとん、甘栗、栗鹿子、栗羊羹を楽しむという風習も今に受け継がれています。
重陽の節句の食べ物のまとめ
| 別名 | 由来 | 食べ物 |
| 菊の節句 | 宮中 | 菊酒・菊のおひたし・菊の和え物など |
| 栗の節句 | 民間 | 栗ご飯・栗きんとん・甘栗・栗鹿子・栗羊羹など |
さいごに
この記事では、重陽の節句の意味や食べ物について、簡単にご紹介してきました。重陽の節句は、他の4つの節句よりも目立たない存在かもしれません。
それは、現在の9月9日は秋を楽しむというよりも、残暑厳しい季節だからではないでしょうか。
昔と今の季節感は異なるので、菊の節句とか栗の節句とか言われてもピンとこないかもしれませんし、重陽の節句の食べ物も昔よりはなじみが薄くなってきています。
でも9月9日の重陽の節句に、菊の花を活けて栗ご飯を楽しむのも風情が感じられて良いですね。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク