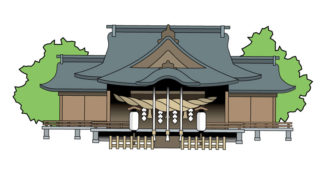藤堂高虎と豊臣秀長の関係を年代順にわかりやすくお伝えします!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
藤堂高虎と豊臣秀長
この記事では、藤堂高虎と豊臣秀長の関係を年代順にわかりやすくお伝えします。藤堂高虎(とうどうたかとら、1556年~1630年)は、戦国時代末期~江戸時代初期に活躍した武将です。
藤堂高虎については有名なことが二つあります。
まず、藤堂高虎は今治城や伊賀上野城など多くの城を築いたことで知られていて、加藤清正や黒田孝高とともに築城三名人の一人に数えられていること。
もう一つは、藤堂高虎は15歳から亡くなるまで、浅井長政⇒阿閉貞征⇒磯野員昌⇒津田信澄⇒豊臣秀長・秀保⇒豊臣秀吉・秀頼⇒徳川家康・秀忠・家光と主家を七度も変えたことです。
時は戦国時代、自分が立身できなければ主家を見限るのは珍しいことではなく、こうした「渡り奉公人」は藤堂高虎に限らず数多く存在しています。
しかし藤堂高虎は主家を変えることで自らの立場を強くし、最後は約30万石を領有する津藩の祖となります。
一方、豊臣秀長(1540年~1591年)は豊臣秀吉の弟で、豊臣秀吉の天下統一を支えるうえで重要な役割を果たしています。
豊臣秀長は冷静で温厚な人柄で知られ、内政・外交・軍事の各分野に優れた能力を発揮し、最後は大和国を中心に110万石を有する大大名となり、「大和大納言」と称された人物です。
ただ、豊臣秀長は若くして病気で亡くなり、その後の豊臣秀吉は独断専行が目立つようになり、豊臣秀吉の死後は豊臣家そのものが衰退し、1616年に滅亡しています。
藤堂高虎が豊臣秀長に仕えたのは1576年で藤堂高虎20歳の頃、そして豊臣秀長の死によりその関係が終わったのは1591年で藤堂高虎35歳の頃。
豊臣秀長と藤堂高虎の主従関係は僅か15年ですが、この二人には強い関係があったようです。
それでは、藤堂高虎と豊臣秀長の関係を、藤堂高虎が豊臣秀長に仕える前から、豊臣秀長が亡くなった後までを含めて年代順にわかりやすくお伝えします。
スポンサーリンク
藤堂高虎が豊臣秀長に仕え大名になるまで
1556年、藤堂高虎は近江国で生まれます。藤堂高虎は幼少のころから体格に恵まれ、15歳で早くも浅井長政に仕え、武功も上げています。
しかし同僚と諍いを起こし逃走、その後に仕えた阿閉貞征・磯野員昌・津田信澄の家中でも諍いを起こしたり、将来に見込みがないと判断して退去。
そして5人目の主人である豊臣秀長に仕えるようになったのが1576年、 藤堂高虎20歳の頃です。
豊臣秀長は藤堂高虎が主家を何度も変えていることも、扱いにくい人物であることも知っていたはずです。
しかし、豊臣秀長は藤堂高虎を300石で召し抱えます。
これは豊臣秀長が藤堂高虎の才能を見出したためとも言われています。
実際、藤堂高虎は豊臣秀長の元で才能を開花。
武将としては、1583年の賤ヶ岳の戦いや、1585年~1587年の四国征伐・九州征伐などに従軍して戦功をあげています。
また、この時期の藤堂高虎は安土城・和歌山城・大和郡山城などの築城に携わり、築城技術を磨いています。
そうした軍事・土木面での才能を発揮した藤堂高虎は1587年、豊臣秀長に仕えてから僅か11年、31歳で紀伊粉河領主として2万石を与えられ大名になっています。
スポンサーリンク
藤堂高虎が出家するまで
藤堂高虎が大名になる前年の1586年頃より豊臣秀長は体調を崩し、1590年の小田原征伐では豊臣秀長に代わり小田原征伐に参陣しています。しかし、翌1591年に豊臣秀長は病死し、豊臣秀長と藤堂高虎の15年にわたる主従関係は終わりを迎えます。
それでも藤堂高虎は主家を離れることはありませんでした。
ところで、豊臣秀長には実子はいませんでしたが、男子の養子は2人いました。
最初の養子は1582年に迎えた仙丸です。
時期は本能寺の変の直後、織田家重臣の丹羽長秀の歓心をかうため、豊臣秀吉に命じられ丹羽長秀の子の仙丸を養子としています。
2人目の養子は、豊臣秀長の甥にあたる豊臣秀保で13歳、豊臣秀吉の死の間際に養子に迎えいれています。
当初、豊臣秀長の後を継ぐのは仙丸の可能性もありましたが、実際には豊臣秀長と血縁関係にある豊臣秀保が後継になります。
そこで困ったのが仙丸の扱い。
藤堂高虎は仙丸を迎え入れ、藤堂高吉とします。
藤堂高虎の死後、後継となったのは実子の藤堂高次です。
藤堂高吉は藤堂本家を継ぐことはありませんでしたが、藤堂高吉の家系は大名として明治維新を迎えています。
さて、豊臣秀長の養子を迎え入れ、豊臣秀長の後継となった豊臣秀保を支え続けた藤堂高虎ですが、1595年に豊臣秀保は病死して大和豊臣家は断絶。
藤堂高虎は高野山へ出家しています。
豊臣家から徳川家へ
藤堂高虎は大和豊臣家の断絶に伴い、一度、豊臣家を離れますが、豊臣秀吉の命により復帰、伊予国三郡の7万石を与えられ再び豊臣家に仕えることになります。そして、1998年に豊臣秀吉が亡くなった後は、徳川家康に急接近。
1600年の関ヶ原の戦いでは東軍として出陣し、戦後に伊勢・伊賀を与えられ32万石の大名になっています。
1616年、徳川家康が亡くなった後は、2代将軍徳川秀忠、3代将軍徳川家光に仕え、1630年に江戸の藤堂藩邸で74歳の生涯を閉じます。
藤堂高虎が徳川家康に接近した理由ははっきりとはわかりません。
ただ、1586年関白豊臣秀吉は、上洛する徳川家康のために屋敷を造ることを豊臣秀長に指示し、豊臣秀長は藤堂高虎を作事奉行に任じます。
しかし設計図の内容に警備上の不具合があるとして、藤堂高虎は設計変更し、変更によって増大した費用は藤堂高虎自身の持ち出しとします。
上洛をした徳川家康が設計図と異なることに気づき、藤堂高虎にその理由を問いただします。
藤堂高虎は、徳川家康に万が一のことがあれば、それは豊臣秀長の責任。
主人に迷惑はかけられないので、一存で変更したと答え、それを聞いた徳川家康は藤堂高虎の心遣いに感謝したという逸話があります。
こうした、藤堂高虎と徳川家康の関係性が、後に藤堂高虎が徳川家に仕えるようになった理由の一つにあげられるのかもしれません。
まとめ

この記事では、藤堂高虎と豊臣秀長の関係を、藤堂高虎が豊臣秀長に仕える前から、豊臣秀長が亡くなった後まで、年代順にわかりやすくお伝えしました。
藤堂高虎が豊臣秀長に仕えた期間は15年で長いとは言えません。
しかし豊臣秀長が藤堂高虎の才を見出し、藤堂高虎自身もそれに応え、結果として藤堂家は大名として明治維新まで続くことになります。
そして、豊臣秀長に仕えている間に築城技術を磨いた藤堂高虎は、現在でも築城三名人の一人として知られています。
藤堂高虎は「渡り奉公人」として主家を何度も変えていますが、藤堂高虎の本質はむしろ忠義の武将と言える存在で、豊臣秀長死後も大和豊臣家断絶まで主家を支え続けています。
豊臣秀長と藤堂高虎の関係は、戦国時代の中でも特に深い主従関係と言えるのではないでしょうか。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク