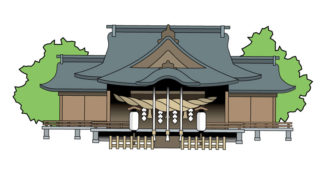前田利家の城を年代順に一覧で!それぞれの特徴もお伝えします

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スポンサーリンク
前田利家の城
この記事では、前田利家が居城とした城を年代順に一覧でご紹介するとともに、それぞれの城の特徴をお伝えします。前田利家(1539年頃~1599年)は戦国時代末期の武将で、織田信長に仕えて頭角を現し、豊臣政権では五大老の一人に任ぜられ、豊臣秀吉死後は徳川家康に対抗できる存在になります。
ただ豊臣秀吉が亡くなった8か月後に病死し、徳川家康は1600年の関ヶ原の戦いを経て江戸幕府を創設します。
それでも前田利家は加賀100万石の祖と称され、前田家は幕末まで大藩を治めることになります。
それでは、最初に前田利家の城を年代順に一覧でご紹介し、そのあとにそれぞれの城の特徴をお伝えします。
スポンサーリンク
前田利家の城一覧
| 荒子城 | 愛知県名古屋市中川区荒子 | 1539年~1575年頃 |
| 府中城 | 福井県越前市 | 1575年~1581年頃 |
| 七尾城 | 石川県七尾市 | 1581年~1582年頃 |
| 小丸山城 | 石川県七尾市 | 1582年~1583年頃 |
| 金沢城 | 石川県金沢市 | 1583年~1599年 |
スポンサーリンク
荒子城
愛知県名古屋市中川区荒子 1539年~1574年代頃荒子城は前田利家の父前田利春が築いた城で、前田利家はこの城で生まれます。
ただ、荒子城は土地が狭い平城で、堀があるとはいっても防御力は弱く、城というよりも砦程度の規模。
前田家の生活の場としての役割を果たしていたと考えられています。
前田利家は前田家の次男でしたが、兄の前田利久が病弱であったため、織田信長の命により1569年に前田家の当主となり荒子城の城主になります。
もっとも前田利家が当主となった頃は、織田信長が足利義明を擁して幕府を再興した時期で、周囲には数多くの敵がいました。
そのため前田利家も、織田信長の家臣として犬山城や清須城などを起点として、各地に転戦していたので、荒子城で落ち着いている時間はほとんどなかったと思われます。
この時期、前田利家は「槍の又左」の異名を得るほどの活躍をみせ、織田家内部での地位を高めていきます。
なお1575年になると、それまでの活躍を認められ越前府中十万石を与えられたため、前田利家は荒子城をでます。
さらに1581年に前田利家の長男前田利長も越前に移ったことで、荒子城は廃城になります。
荒子城の遺構はなく、現在は富士権現社や城址碑などがあります。
府中城
福井県越前市 1575年~1581年頃朝倉義景が織田信長に滅ぼされ、朝倉氏旧領のうち越前2郡約10万石が、前田利家・佐々成政・不破光治の3人に与えられます。(府中三人衆)
三人はそれぞれに城を持ちますが、前田利家が築いたのが府中城です。
後世の発掘調査で、府中城には大規模な堀や石垣があり、さらに居館も大きなものであったと考えられています。
その後、前田利家は能登国に封じられるとともに、府中城は前田利長に与えられ、さらにその後は城主が入れ替わり、江戸時代には越前松平藩の家老が治め、明治を迎えます。
明治時代になると城は破却され、現在は市庁舎などになり、城址碑や復元された石垣の一部があります。。
七尾城
石川県七尾市 1581年~1582年頃1581年、織田信長の命により前田利家は能登国を与えられます。
その時に居城としたのが七尾城(ななおじょう)です。
七尾城は元は畠山氏の居城で、7つの尾根を活かした堅城として知られ、難攻不落の山城として日本五大山城の一つに数えられていました。
もっとも、防御に優れているとはいっても政務には不向きだたため、前田利家は麓に小丸山城を築いて移っています。
前田利家の後は、子の前田利政が城主となりますが、1589年に廃城となります。
なお、本丸だった場所には野面積みの石垣など遺構が数多く残り、国の史跡に指定されています。
日本五大山城とは
七尾城(ななおじょう)
春日山城(かすがやまじょう)
観音寺城(かんのんじじょう)
小谷城(おだにじょう)
月山富田城(がっさんとだじょう)
小丸山城

石川県七尾市 1582年~1583年頃
政務に不向きな七尾城に代わり、七尾湾を臨み海運に強い場所に築いたのが小丸山城です。
小丸山城は丘陵地にある平山城ですが、海と川に囲まれた防御力の高い城と言われています。
小丸山城は、前田利家が加賀国に拠点を移すまでの政治経済の中心となった場所で、現在は小丸山城址公園として整備され桜の名所として知られています。
金沢城
石川県金沢市 1583年~1599年1583年、前田利家は加賀国に拠点を移します。
最初に居城としたのは、尾山御坊(おやまごぼう)です。
尾山御坊は旧一向一揆の拠点であり、一向一揆勢力が建てた寺院形式の城郭です。
尾山御坊は金沢城改築までの一時的なものであり、現在は尾山神社として整備されています。
そして、改築が終わった金沢城に入城した前田利家は、亡くなるまでここを居城としています。
金沢城も尾山御坊の一部でしたが、前田利家は大規模な城郭改修を実施します。
金沢城は、寒暖差に強い鉛瓦や、強度と防火性に優れた海鼠壁などを採用し、北陸の気候に適した改修を行っています。
また金沢城は、野面積みや切り込みハギ積みなど多様な石垣が見られることでも知られています。
さらに、石川門・三十間長屋・鶴丸倉庫などは国の重要文化財に指定され、その他復元された建造物なども伝統技術が用いられています。
前田利家は、金沢城を流通・防衛・政治の中心として整備し、江戸時代を通して加賀百万石を統治する拠点となっています。
なお、金沢城は現在も金沢城公園として保存され、観光拠点として多くの人が訪ねる場所になっています。
まとめ
この記事では、前田利家の城を年代順に一覧でご紹介するとともに、それぞれの城の特徴も合わせてお伝えしました。前田利家は織田信長の家臣、次いでかつては自分より身分が下だった豊臣秀吉に臣従します。
織田信長は横死し、子孫の多くは没落。
豊臣秀吉が亡くなった後は、豊臣家そのものが滅亡。
その中で前田利家は戦国時代を生き残り、加賀100万石の礎を築いています。
前田利家こそ、戦国大名の勝ち組だったのではないでしょうか。
■合わせて読みたい
スポンサーリンク
スポンサーリンク